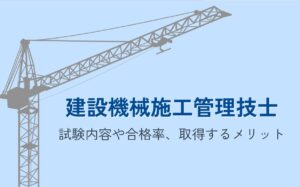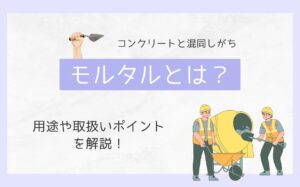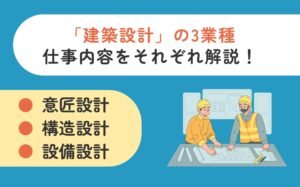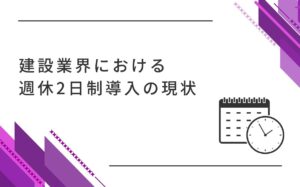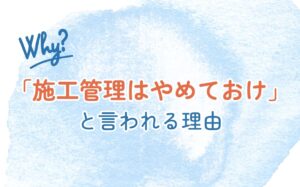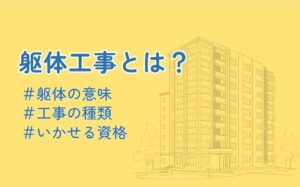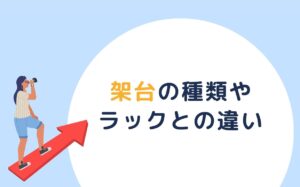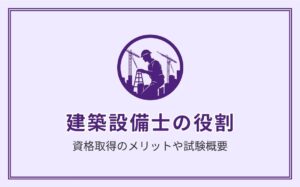一定規模のボイラーを有する施設では、ボイラーを運転する際に国家資格であるボイラー技士を配置するよう法律で定められています。ボイラー技士資格は、運転管理ができる施設の規模によって二級・一級・特級と3種類に分かれています。
今回は、その中で運転管理できる施設数がもっとも多く有用性の高い一級ボイラー技士について解説します。
一級ボイラー技士とは
ボイラー技士とは、ボイラー設備の運転管理と保守を行うための資格を持つ人のことです。
ボイラーとは、水を燃料などで沸かしてお湯や水蒸気を作り出す装置の総称です。ボイラーが設置されている施設は、温水プールや温泉施設など一般利用できる施設から大規模な工場までさまざま。大規模なオフィスビルや工場、病院など公共性の高い施設にも多く設置されており、ボイラー技士はその施設ごとに選任する必要があります。
ボイラーの大きさは伝熱面積で表され、伝熱面積3平方メートル以上のボイラーを取り扱う際には、ボイラー技士の資格を持った人が作業に従事しなければなりません。一級ボイラー技士の資格を取得すると、ボイラーの伝熱面積が25平方メートル以上500平方メートル未満の設備を取り扱えるようになります。
現在、運転時のコストが安い貫流ボイラーが多くの大規模施設に普及しています。貫流ボイラーは250平方メートル以上の大型ボイラーとなるため、取り扱いには一級ボイラー技士資格が必要となります。
一級ボイラー技士の仕事内容
ボイラーの運転には、高圧の蒸気やガスなどの可燃性燃料を使用します。一級ボイラー技士は、こうした燃料を使う伝熱面積25平方メートル以上500平方メートル未満のボイラーを日常的に安全に運転することが大きな役割となります。
運転中のボイラー設備を定期的に巡回して運転記録を取る、異常がないかを確認するといった業務が、日常的な運転管理となり、運転中に異常が発生した場合、安全にボイラーを停止するのもボイラー技士の役割です。停止後に異常箇所の修理まで行うこともあります。
ボイラーの定期点検は法律で義務化されているため、必ず行わなければなりません。分解による点検になるとメーカーや整備業者に委託するケースも出てきますが、それらの業務がきちんと行われているかを確認するのもボイラー技士の仕事です。
二級ボイラー技士・特級ボイラー技士との違い
ボイラー技士には、一級のほかに二級・特級の資格があります。
二級ボイラー技士は一級ボイラー技士の下位資格となり、伝熱面積25平方メートル未満のボイラーの取り扱いが可能です。一級ボイラー技士と比較するとかなり小規模なボイラーしか扱えない資格となりますが、受検資格で実務経験がいる一級ボイラー技士に対して、二級ボイラー技士は、年齢、性別、実務経験に関係なく受検できます。ただし、資格試験に合格しても、免許を取得するには18歳以上で実技講習を受けなければなりません。
特級ボイラー技士は、一級ボイラー技士の上位資格です。一級ボイラー技士はすべての貫流ボイラーが扱えますが、特級ボイラー技士は貫流ボイラーだけでなくすべての種類・大きさのボイラーを取り扱うことができます。
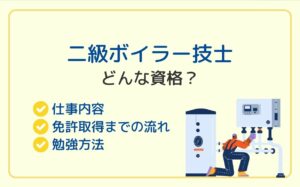
一級ボイラー技士の試験概要
では、一級ボイラー技士の試験概要を見ていきましょう。
受検資格
一級ボイラー技士の受検資格は以下の表の通りで、受検資格があることを証明する書類がそれぞれ必要です。
| 受検資格 | 必要書類 |
|---|---|
| 二級ボイラー技士免許を受けた者 | 二級ボイラー技士免許証の写し |
| 大学(短期大学を含む)、高等専門学校を卒業した者で、1年以上の実地修習を経たもの | 卒業証明書(蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの) |
| 熱管理士・エネルギー管理士(熱)免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの | エネルギー管理士免状の写し 実地修習結果報告書の写し |
| 海技士(機関3級以上)免許を受けた者 | 海技士免状の写し |
| ボイラー・タービン主任技術者(1種・2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | ボイラー・タービン主任技術者(1種・2種)免状の写し 事業者証明書 |
| 保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | 汽かん係員試験合格証の写し 事業者証明書 |
参照:公益財団法人安全衛生技術試験協会|受験資格(一級ボイラー技士)
上記の通り、二級ボイラー技士を取得して業務に携わっていた人、大学や高等専門学校でボイラーに関する専門的な教育を受けた人、関連する資格であるエネルギー管理士(熱部門)の資格を取得した人などが対象となります。
試験の費用や日程・時間・出題範囲
一級ボイラー技士試験は、公益社団法人安全衛生技術試験協会が主催しており、試験は協会の各支部で2~3か月に一回行われています。受検費用は8,800円。会場は北海道、東北、関東(市原と東京の2か所)、中部、近畿、中国・四国、九州と全国の会場で行われるので、近くの会場で受検しましょう。試験の日程によっては開催されない会場もあるので注意が必要です。
令和6年度、令和7年度の出題範囲や試験のスケジュールは以下の通りです。
| 試験科目 | 出題数(配点) | 試験時間 |
|---|---|---|
| ボイラーの構造に関する知識 | 10問(100点) | 12:30~16:30 (4時間) |
| ボイラーの取扱いに関する知識 | 10問(100点) | |
| 燃料及び燃焼に関する知識 | 10問(100点) | |
| 関係法令 | 10問(100点) |
令和6年度(令和6年11月~令和7年3月)
| 試験会場 | 試験日程 | |
|---|---|---|
| 北海道センター | 令和7年1月23日(木) 令和7年3月11日(火) | |
| 東北センター | 令和7年1月23日(木) 令和7年3月11日(火) | |
| 関東センター | 市原 | 令和7年1月23日(木) |
| 東京 試験場 | 令和7年1月23日(木) | |
| 中部センター | 令和7年1月23日(木) 令和7年3月11日(火) | |
| 近畿センター | 令和7年3月11日(火) | |
| 中国四国センター | 令和7年1月23日(木) 令和7年3月11日(火) | |
| 九州センター | 令和7年1月23日(木) 令和7年3月11日(火) | |
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)
| 試験会場 | 試験日程 | |
|---|---|---|
| 北海道センター | 令和7年6月5日(木) 令和7年9月5日(金) 令和7年11月19日(水) 令和8年1月22日(木) 令和8年3月13日(金) | |
| 東北センター | 令和7年6月5日(木) 令和7年11月19日(水) 令和8年1月22日(木) 令和8年3月13日(金) | |
| 関東センター | 市原 | 令和7年6月5日(木) 令和7年9月5日(金) 令和7年11月19日(水) 令和8年1月22日(木) 令和8年3月13日(金) |
| 東京 試験場 | 令和7年6月5日(木) 令和7年9月5日(金) 令和8年3月13日(金) | |
| 中部センター | 令和7年6月5日(木) 令和7年9月5日(金) 令和8年1月22日(木) 令和8年3月13日(金) | |
| 近畿センター | 令和8年1月22日(木) | |
| 中国四国センター | 令和7年6月5日(木) 令和7年9月5日(金) 令和7年11月19日(水) 令和8年1月22日(木) 令和8年3月13日(金) | |
| 九州センター | 令和7年6月5日(木) 令和7年9月5日(金) 令和8年1月22日(木) 令和8年3月13日(金) | |
参照:公益財団法人安全衛生技術試験協会|日程(一級ボイラー技士)
| 試験時間・実施場所 |
|---|
| 午後0時30分~午後4時30分まで 北海道安全衛生技術センター(北海道) 東北安全衛生技術センター(宮城県) 関東安全衛生技術センター(千葉県市原市) 関東安全衛生技術センター 東京試験場(東京都) 中部安全衛生技術センター(愛知県) 近畿安全衛生技術センター(兵庫県) 中国四国安全衛生技術センター(広島県) 九州安全衛生技術センター(福岡県) |
| 受検費用 |
| 8,800円 |
出題科目は、ボイラー構造に関する知識、ボイラーの取り扱いに関する知識、燃料及び燃焼に関する知識、ボイラーに関する関連法規の4つです。試験時間は分かれておらず、4科目で4時間、休憩なしの実施となります。1科目10問ずつ、合計40問出題され、試験開始後1時間で退室可能となります。
受検申請と合格後の手続き
受検の申請書類は、公益財団法人安全衛生技術試験協会、安全衛生技術センター、一般社団法人日本ボイラ協会などで入手できます。申請は受検の2か月前から受け付けが始まり、本人確認書類などの必要書類と証明写真、受検申請書、試験手数料の振り込み領収証を郵送して申請します。
一級ボイラー技士の試験に無事合格しても、免許を取得した状態ではありません。合格後、所定の実務経験証明書類と共に免許交付の申請を行わなければいけません。書類に不備がなければ免許が交付されます。
試験の合格率と難易度
令和5年度の一級ボイラー技士の合格者数は、以下の通りです。
| 年度 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 4,535人 | 2,248人 | 49.6% |
受検者数4,535人に対して合格者数は2,248人、割合にして49.6%でした。受検者数の約半数が合格する試験ですが、試験はボイラーの構造や実務を行う際に重要な専門的な内容であり、まったく勉強せずに受検しても合格できません。しっかりと準備をして臨みましょう。
免許取得の注意点
前述の通り、一級ボイラー技士の免許は合格するだけでは取得できません。ボイラーの取り扱い業務を2年以上、もしくはボイラー取扱作業主任者の経験を1年以上積まなければなりません。それらを証明できる実務経験従事証明書と一級ボイラー技士試験合格証明書を提出して免許の交付を申請しなければならない点に注意しましょう。
一級ボイラー技士を取得するメリット
続いて、一級ボイラー技士の資格を取得するメリットを4つご紹介します。
活躍の場が広がる
二級ボイラー技士の資格だけでもボイラーに関する仕事への従事は可能です。しかし、一級ボイラー技士の資格を取得すると取り扱えるボイラーが増えるため、より一層活躍の場が広がります。
需要が安定している
一級ボイラー技士が取り扱えるボイラーの中には、現在主流となっている貫流ボイラーが含まれています。貫流ボイラーは大型施設や火力発電所など公共性の高い設備にも導入されており、資格を持った人の求人も安定して出されています。
生活に欠かせないものであり、需要が安定しているため、突然仕事がなくなるといった心配が少ないです。
収入アップが狙える
一級ボイラー技士になるには、資格試験に合格するだけでなく実務経験もいります。そのため誰でも資格を持てるわけではありません。極めて専門性の高い存在として昇給が期待できるほか、資格に対する手当が会社から出されることもあります。
転職の際に有利になる
一級ボイラー技士の資格を持っていると、転職の際にスキルの公的な証明となります。資格取得には実務経験が要件となっているため、一級ボイラー技士を取得しているとボイラーのスペシャリストとして評価され、転職市場での評価が高まるでしょう。
一級ボイラー技士の勉強方法やポイント
一級ボイラー技士の資格を取得する際には、受検勉強は避けては通れません。ここでは、勉強を継続するコツやポイントをご紹介します。
インプット・アウトプットのバランスを意識する
勉強する際には、知識を入れ込むインプットと、頭に入れた知識をノートに書くなどして取り出すアウトプットのバランスが重要です。ただし、インプットとアウトプットを同じ時間やれば覚えられるものではありません。集中できる時間帯を見つけて勉強する、学校の勉強のようにインプットばかりを行わないといったことを心掛けましょう。
過去問で試験の傾向を把握する
資格試験の多くは過去問から繰り返し出題されています。まったく同じでなくても、似た傾向の問題が出題されることが多いため、過去問を解くことは極めて重要な勉強法の一つです。過去問を解いて間違えた箇所はしっかり見直し、試験本番には同じ傾向の問題が出ても間違えないようにしましょう。
安全衛生技術試験協会のWebサイトでは試験問題が公開されているため、勉強の際にはぜひ参考にしてください。
間違えやすい箇所は見直しをする
過去問や試験の予想問題集などで間違えた部分があったら、参考書などを頼りに知識を見直すようにしましょう。問題を解いて間違えたということは、間違った知識を持ってしまっているということです。試験までにこうした箇所をしっかり見直していくことで正しい知識が身につき、試験の正答率も上昇していきます。
事前講習を受けてみる
一般財団法人日本ボイラ協会の各支部では、一級ボイラー技士試験の試験準備講習会が開催されています。独学の試験勉強だけでは不安な場合は講習会を受講してみましょう。
まとめ
一級ボイラー技士の資格で取り扱うことができるボイラーは、病院や大型オフィスビルなどの重要施設や火力発電所など社会インフラを担うものまでさまざまです。二級ボイラー技士で扱える範囲のボイラーは小型ボイラーであり、近年では電気ヒーターなどに置き換えられているケースも多くなってきていますが、一級ボイラー技士が取り扱えるボイラーには代替の技術がなく、将来的に安定した需要が見込めます。
高い需要があり将来性もある一級ボイラー技士の資格取得を、ぜひこの機会に目指してみてはいかがでしょうか。
マンパワーグループコンストラクション株式会社
関東・関西を拠点に、日本全国の建設会社に技術者を派遣している人材派遣会社です。
未経験者からベテランまで幅広く採用し、一人ひとりの希望に沿った案件をご提案いたします。
当社において最も大切にしている価値観は『技術者ファースト』。
一人ひとりが「自分と向き合ってもらえている」と感じてもらえるよう、営業・サポート担当の2名体制で本人をサポートいたします。
キャリアチェンジや異業種からの転職など、何でもお気軽にご相談ください!
マンパワーグループコンストラクション株式会社 コーポレートサイト